●
望月町周辺 ●●● Sep. 27,2003 with FinePix500
■ 望月宿
中山道の宿場町として栄えた望月町は、小諸駅からバスで約35分の所にあります。鹿曲川が流れるこの街には、本陣・脇本陣・問屋そして29軒の旅籠屋が軒を連ねていたそうです。
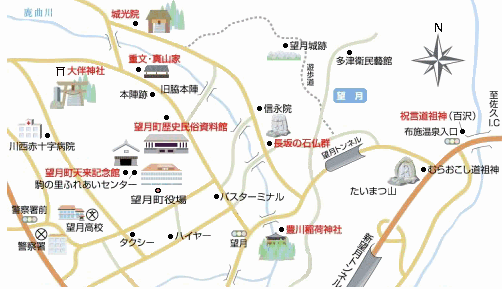
★ 望月バスターミナル

望月の玄関です。小諸駅から一時間に一本位の間隔でバスが出ています。
★ 望月町 歴史民族資料館 開舘 9:00〜16:30 観覧 300円 (天来記念館と共通
500円)

「郷土の歴史と文化」,「中山道望月宿」,「人々の暮らしと伝統」の3テーマで、実物・模型・パネルなどを展示。平石遺跡の復元住居や民家の一室を再現したコーナーもある。
★ 天来記念館 開舘 9:00〜16:30 観覧 300円 (歴史民族史料館と共通
500円)
 |
明治5年に望月で生まれた比田井天来の業績を伝えるために開かれた記念館で、天来と妻の比田井小琴の書や筆・硯などの遺品,教本・現行が展示されている。 |
★ 脇御本陣
★ 真山家
 |
旅籠と問屋を兼ね、幕末には名主を務めた真山家の住宅(重文)が今も残っている。「大和家」の古い看板を掲げた母屋は明治3年の建築で、間口6間(約11m)、1階に半間幅の土庇を付け2階は出桁造、椀木に繰形紋様が刻まれている。 |
★ 大伴神社

望月の牧の鎮守社としてまつられた延喜式社で、佐久三社の一つに数えられている。鳥居脇にある石の社標は比田井天来の筆。
★ 城光院

望月城主の望月遠江守光垣が1475年に菩提寺として開いた曹洞宗の古刹。本堂は享和年間(1801〜1804)建立の本堂があり、その前に石造十王像が並んでいる。山門をくぐった左手には1680年の石造庚申塔もある。
★ 望月城址

城光寺の裏山一帯が、平安から室町時代の豪族望月氏が本拠とした山城の跡。望月氏は鎌倉時代に眼下に見下ろす天神城を築城し落城後室町時代に望月城を築城したとされており、戦国時代に落城している。
★ 信永院

1532年に望月左衛門尉信永が開いた曹洞宗の古刹。樹齢500年といわれる、本堂の前の榧の大木は根本から十数本の幹が出た珍しいもの。
★ 長坂の道祖神

望月には140体もの道祖神がまつられているが、これもその一つだそうです。
★ 豊川稲荷

鹿曲川の絶壁の上に朱塗りの社殿が建っている。
★ 弁天窟
 |
豊川稲荷真下の絶壁を穿って弁財天をまつったところで、絶壁に張り付くように赤い屋根の堂が建っている。弁財天は室町末期の永正年間(1504〜1521)に琵琶湖の竹生島から勧請したものと伝えられる。堂の上の岩壁に刻まれた「蟠龍窟」は、本陣の主で書家だった大森曲川の書である。ここへの入口に向井去来の句碑も立っている。 |
■ 茂田井宿
望月から旧中山道を3Kmほど西に行くと茂田井宿があります。江戸時代に望月宿と芦田宿との間の宿だったところで、半農半宿で栄えていたそうです。

突然現れる当時の雰囲気そのままの町並みには、圧倒されっぱなしでした。国道142号線がこの宿場を避けるように建設されたため宿場がそっくり残ったそうですが、それよりも、この景観を今なお維持し続けている2軒の造り酒屋の努力のおかげと思います。

★ 武重本家酒造

昔の酒造道具や酒器が展示されいて自由に見学できる。若山牧水の歌碑も立っている。
★ 茂田井名手の館 開舘 9:00〜16:30
昔ながらの建物の中に、多くの貴重な品々が展示されている。無料なのが嘘みたいです。

・名手の館書道舘
祖比田井天来先生をはじめ、ご一門の書が展示されている。
・大澤酒造民族資料館
土蔵の中に守られ残されてきた器具・巻物等の貴重な民族・歴史資料が展示されています。
・しなの山林美術館 (写真右)
当地出身の大澤邦雄画伯とその師の作品を中心に約150点の絵画を展示する美術館。
● 次へ → 小諸
● 戻る → 佐久(臼田周辺)
● 長野県Top → 何故か近場の長野県