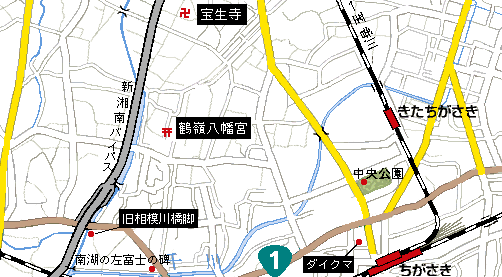
■ 茅ケ崎駅北口
 Canon
NewF1&KironZooM
Canon
NewF1&KironZooM■ ダイクマ(ヤマダデンキ)
 Canon
NewF1&KironZooM
Canon
NewF1&KironZooMヤマダデンキに吸収合併されてしまったとはいえ、茅ケ崎といえば、やっぱりダイクマです。今は昔、毎週金曜に入るダイクマのチラシ広告には、胸を高鳴らせたものでした。
●●● 茅ケ崎北部 2003,
July〜 with FinePix 500
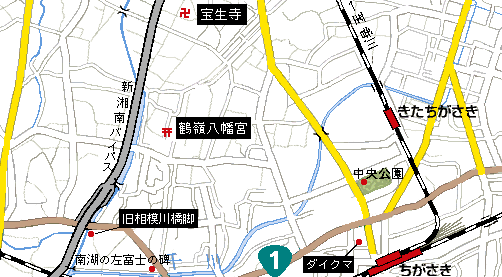
■ 茅ケ崎駅北口
 Canon
NewF1&KironZooM
Canon
NewF1&KironZooM
■ ダイクマ(ヤマダデンキ)
 Canon
NewF1&KironZooM
Canon
NewF1&KironZooM
ヤマダデンキに吸収合併されてしまったとはいえ、茅ケ崎といえば、やっぱりダイクマです。今は昔、毎週金曜に入るダイクマのチラシ広告には、胸を高鳴らせたものでした。
■ 中央公園
■ 旧相模川橋脚
 Canon
AL1&TamronZooM
Canon
AL1&TamronZooM
小出川に沿うこの一帯は、永らく水田であったが1923年9月および翌年1月の大震災によって7本の橋脚が地上に出てきた。その後、地下に埋もれたもの3本が発見された。
相模川は、鎌倉時代にはこの辺を流れていたが川すじの変化によって西方へ移ったもので脚脚は土中に埋まったまま700年をへて再び地上に露出したものである。
橋の幅は少なくとも7mくらいと推定され、全国でも数少ない大橋であったと考えられている。
■ 南湖の左富士の碑
| 浮世絵師安藤廣重は、1832年に東海道を旅し、後 続々と東海道53次の風景版画を発表した。その中の一枚に南湖の松原左富士がある。東海道の鳥井戸橋を渡って下町屋の家並みの見える場所の街道風景を写し、絵の左には富士山を描いている。東海道のうち、左手に富士山を見る場所は、ここと静岡県吉原の二ヶ所が有名。昔から茅ケ崎名所の一つとして南湖の左富士が巷間に知られている。 |
| 西にのびた低台地(海抜12m)の先端にあたるここからは、昭和38年11月と翌年8月の発掘調査で貝塚と竪穴住居址(縄文時代前期・黒浜式期)が見つかっています。 貝塚の貝層はごく小規模で、廃棄された竪穴住居址内に堆積したものでした。貝殻はヤマトシジミを主に(九割以上)チョウセンハマグリ・マガキ・バイ・サザエなどが見られ、また、少量の魚骨や獣骨・石器類も出土しました。 竪穴住居址は地表面から約1mの深さで床面にたっし、その平面形は台形で、中央西寄りに炉址があり、壁の周囲には溝がめぐっていました。柱穴は全部で六つが中央部と壁溝内に規則的に配されていました。 |
| 昔、この地に「海円院」という寺院があって、1182〜1190頃に兵火によって焼け落ちたと「上正寺略縁起」などに記されています。実際、この辺りは七堂伽藍跡と呼ばれ、古い布目瓦や礎石が出土していて、これらの記録が根拠のない話ではないことを伺わせていました。 昭和53年7月に茅ケ崎市史編さん事業の一環として行なわれた試掘調査の結果、瓦の破片燈明皿として使われた多量の土師器その他が出土して、このあたりが古代寺院の跡であることは明らかとなりました。寺域などはまだ判明しませんが、瓦の分布によると、かなり広大なものであったことが想定されています。 ちなみに、石碑の土台石は、当時の礎石です。 |
| ここに見られる二つの高塚は古墳時代後期の古墳です。これらの存在はかなり以前から知られていましたが、その実体は不明でした。 昭和50年3月に行なった調査の結果、南の一基は、その外形と裾野をめぐる周溝の形(長方形)から前方後方墳と考えられています。北の1基は円墳です。 2基の墳丘は北に向かって穏やかに傾斜する屋根状の大地に、自然の地形を利用して約19mの間隔で造られています。 これらは墳丘の規模からみて、茅ケ崎北部を中心とした小領域を支配する中・小首長(豪族)2世代の墓と考えられます。 |