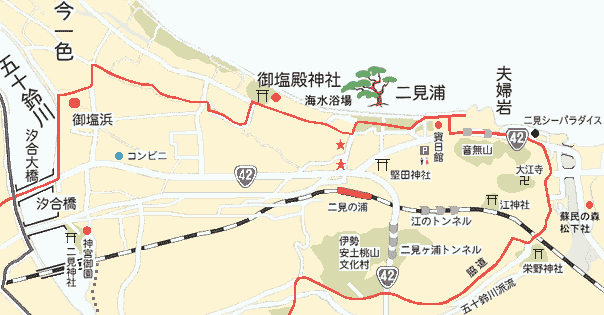▼▼▼▼ 伊勢 ー 2日目 Sep.
7, 2008 with NIKON D50 &
TAMRON 28〜105 F2.8
■ 9月7日〔日) スケジュール
??:?? 二見浦 → 伊勢 ??:?? JR
×××××× 伊勢観光 ××××××××
16:02 伊勢 → 名古屋 17:41 快速みえ
17:58 名古屋 → 豊橋 18:45 JR
18:53 豊橋 → 浜松 19:31 JR
19:40 浜松 → 静岡 20:50 JR
20:52 静岡 → 熱海 22:04 JR
22:08 熱海 → 平塚 22:50 JR
×××××× 二見浦
観光 ××××××
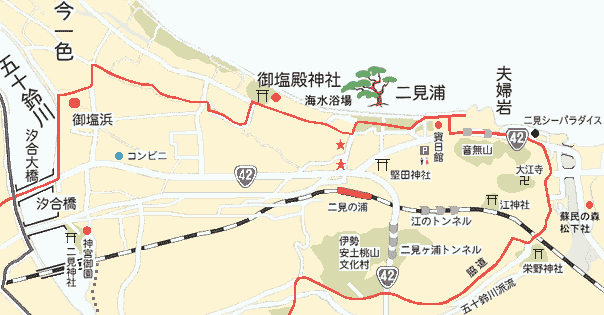
● 二見興玉神社・夫婦岩
猿田彦大神をまつり、縁結び,夫婦円満,交通安全などに霊験あらたかとされる。大神の使いが蛙だといわれるところから、境内には蛙の置物がたくさん飾られている。境内には海の神をまつる竜宮社,岩窟の天ノ岩屋もある。

・・・4〜9月の間は、両岩の間から日が上るとガイドブックに書いてあったのに......。 次回は、7月に来よう。
● 二見シーパラダイス
 |
二見プラザの中心施設となっている水族館。 |
● 猿田彦石とその付近

太江寺へ向かう途中にありました。
● 太江寺

音無山の東麓にある古刹で、729〜749頃に行基が開いたと伝わっている。鎌倉初期の内宮の袮宜 荒木田成重が再興し、その時に寄進したという木造千手観音坐像(重文)が、江戸時代に再建された本堂に安置されているそうだ。
● 旅館街

駅までの道のりにはこんな風景が続きます。 賓日館(入館300円)とかもあります。
● 二見浦海水浴場
 |
1882年に、日本最初の海水浴場として国指定されたそうな。 |
● 御塩殿神社
五十鈴川の河口近くの海岸には、神宮の塩作りが行われる御塩殿神社が建つ。内宮の所管社で、神宮で使う塩を造るところとして知られている。毎年夏の土用の頃に五十鈴川河口近くの御塩浜で海水を汲み、ここの境内の御塩汲入所へ運び、隣接の御塩焼所で鉄の平釜で煮詰め荒塩が造られる。そして10月5日に神宮の神職が荒塩を三角形の土器に詰めて堅塩に焼き固める「御塩殿祭」が行われる。

● 赤福
 |
いろいろあったようですが、やっぱり有名な赤福ですね。 |
×××××× 伊勢観光 (後半)××××××
● 伊勢駅付近
とりあえず、伊勢うどん(朝飯)でも食べましょうか?

写真左 ここは、朝早くから開いていました。看板によると、TVでも紹介されたことがあるとか。
写真右 卵入りの伊勢うどんです。生卵は、この味にけっこうあうみたいです。
● 日蓮上人誓いの聖跡
 |
詳細はよくわかりませんが、駅前の観光案内板にものってました。
近くに、チェリオの自販機があったことに感動したのは覚えています。 |
● 神宮式年遷宮美術館 開舘 9:00〜16:30 入館 500円
 |
平成5年に行われた式年遷宮を記念して開館した美術館。東山魁夷,高山辰雄,平山郁夫ら現代日本美術界を大表する作家の作品が、一堂に展示されているらしい。 |
● 徴古館 開舘 9:00〜16:30 入館 300円

徴古館は、緑豊かな倉田山の地にあり、春にはツツジで彩られる。伊勢神宮の神殿内に納められた神宝御装束の展示のほか、内宮正宮の模型などで、伊勢神宮を詳しく紹介しているそうだ。
また、写真右の農業館は、水産業の資料を幅広く展示してるらしい。
● 倭姫宮
 |
天照大御神の鎮まる地を伊勢と定め、大和から供奉した垂仁天皇の皇女 倭姫をまつる内宮の別宮で、大正12年に創建された。すぐ近くに倭姫命御陵墓参考地もあるそうだ。 |
● 月読宮
内宮の別宮で、4宮が並んでいる。向かって右から月読尊の荒御魂をまつる月読荒御魂宮,天照大御神の弟 月読尊をまつり、4宮の主宮である月読宮.月読尊の父
伊弉諾尊をまつる伊佐奈岐宮,月読尊の母 伊弉冉尊をまつる伊佐奈弥宮の順で、参拝は月読宮から始めるそうだ。
● 猿田彦神社

天照大御神の孫瓊々杵尊が高千穂に天降った時(天孫降臨)に先導をつとめた猿田彦大神と、後裔の太田命がまつられている。地祭と方除の総社として崇敬されている神社で、本殿の鰹木,欄干.大鳥居と手水舎の柱などが方位を意味する八角形になっている。拝殿正面の中央には、方向を刻んだ八角石柱もある。
● おはらい町通り

おはらい町は、江戸時代に全国各地からの参宮客を泊めた「御師の館」が並んでいた場所。当時は、伊勢神宮で神楽をあげることはできず、御師の館で神楽やおはらいが行われたことから、この名がついたらしい。
町の中ほどにはおかげ横丁があり、連日賑わっている。
● 内宮
・宇治橋と鳥居

五十鈴川に架る宇治橋は、俗界と聖界との境の橋とされている。その橋の外側と内側(神域側)に高さ7.44mの大鳥居がたっている。外側の鳥居は外で宮旧正殿の棟持柱、内側の鳥居は内宮旧正殿の棟持柱で造られたものだそうだ。
・御手洗場,御厩

御裳濯川とも呼ばれる五十鈴川の水際に1602年に徳川綱吉の生母・桂昌院が寄進したという石畳が敷かれている。参拝者は、雨の日には手水舎で手を洗い口をすすぐが、晴れた日はここで清めるのが普通になっているそうだ。
神楽殿前に内御厩,参集殿前に外御厩があり、それぞれ、皇室から牽進された神馬が飼育されてるらしいが、単に団体客の集合場所と化していた。(写真右)
・神楽殿,御稲御蔵

神札授与所として御饌殿がある建物にあり、外宮と同じように雅楽奉奏を受け付けているそうだ。(写真左)
この建物は正殿と同じ唯一神明造。神宮神田で収穫した抜穂の稲が納められているそうだ。(写真右)
・荒祭宮

正宮北側の石段の上に建つ内宮第一の別宮。天照大御神の荒御魂がまつられているそうだ。
・踏まぬ石,風日祈宮

古神宝類を納めた外幣殿から荒祭宮を通じる参道石段の途中にある。石段の敷石の一つが4つにひび割れしており、割れ方が「天」の字に似ているので”天から降った石”といわれ、参拝者は踏まないように避けて歩いているらしい。しかし、それ以前に見つからなかった。
風日祈宮橋を渡った五十鈴橋の対岸にある内宮の別宮で、外宮の風宮と同じ風の神がまつられている。(写真右)
● 小坡美術館 開舘 9:00〜16:00 入館 300円
 |
猿田彦神社の宮司の娘である伊藤小坡の作品を展示した美術館。
小坡は、1877年生まれで、明治から昭和にかけて京都で活躍した日本画家。帝展の入選作や掛け軸など、季節ごとに展示内容が変わるそうだ。 |
● 常夜灯
 |
桜木地蔵の道しるべとともに、こんなものがありました。い |
● 桜木地蔵
 |
この地蔵は、桜の大樹の元に鎮座されていたことから桜木地蔵と名付けられたといわれています。
世の人々を守る霊験と子育て病気よけの妙特も聞こえるこの地蔵は古来より多くの方々の信仰を集めております。正徳2年山田奉行を勤めた大岡越前もこの地蔵を訪れ江戸奉行に江戸奉行に出世したという伝えから、出世地蔵とも呼ばれております。
とのこと |
● 伊勢古市参宮街道資料館 開舘 9:00〜16:30 入館 300円
 |
旧伊勢街道沿いの古市は、江戸時代は遊郭や芝居小屋が立ち並び、精進落としの場として賑わった。往時をしのばせる伊勢歌舞伎の豪華な衣装や、妓楼で使用された什器などの資料が展示されているそうだ。 |
● 寂照寺

1677年に京都知恩院の第37代世寂照知鑑が、徳川秀忠の娘で、豊臣秀頼の正室だった千姫の暮堤を弔うために創建したと伝わる浄土宗の古刹。千姫の位牌や遺品が伝わっているそうだ。
● 長峰神社

長峰神社は、天鈿女命をはじめ、8柱の神様をおまつりしてます。御祭神の後神徳は芸道の守護神として、また福の神としても名神様だそうです。
● 大林寺
 |
信空が1625年に創建した浄土宗の寺。境内には、歌舞伎の「伊勢音頭恋の寝刃」の主人公遊女お紺と福岡貢の墓がある。お紺の墓は1829年に坂東彦三郎が、福岡貢の墓は、昭和4年に実川延三郎が建立したそうだ。 |
といったところで、そろそろ時間がまいりました。
そろそろ帰らねば電車がなくなる..........。
戻る → 伊勢壱
HOMEへ → HOME Document